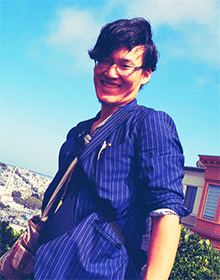後藤晃一[メンタルトレーニングコーチ]
競技スポーツの意義とは?今後の日本社会における価値を見出すために
桜ノ宮高校バスケットボール部や日本大学アメリカンフットボールの事件をはじめとした、競技スポーツの社会的意義は今国民の注目が集まっています。毎年数多くの体罰・ハラスメントの報告が取り上げられています。
こうしたスポーツ指導は勝利至上主義といわれ、選手達の人生すらも左右してしまうほど大きなインパクトを残しているのではないでしょうか。
本記事では、競技スポーツの意義と今後の日本社会における価値を見出すためにスポーツ界でどのような事に取り組んでいけば良いのかについて解説します。
競技スポーツとは?

競技スポーツとは、プレイを上位概念とした運動文化と競争(アゴン)の入り混じった概念であることが報告されています1)。つまり、競技スポーツでは、競争しながら運動しているということになります。
スポーツで社会的人材が育つ日本社会に

スポーツで社会的人材が育つ日本社会になることは、競技スポーツの価値を高めることにつながります。
国際競争力や競争社会という言葉があるように、社会において競争することはごく当たり前で、競い合うことによってよりよい社会にもなり得るからです。
競争することを英語でCompeteと言いますが、語源であるラテン語ではCompetreと表現し、「共に努力すること」を意味します。
つまり、競争の本質は単に勝ち負けを競うことではなく、勝ちを目指す中で切磋琢磨し共に努力することを指すのです。
つまり、競争力が高い人(努力ができる人)を競技スポーツの中で育むことによって、経済的にも影響のある人材育成になる可能性が高いのです。
社会的人材になるスポーツ選手が持つべき成長マインドセットとは?
社会的な人材になる上で、教育界でも注目されている概念としてマインドセットがあります。Carol2) によればマインドセットは2つに大きく分けられていて「成長マインドセット」と「固定マインドセット」があります。
成長マインドセットとは、資質や能力が努力や戦略、他の人からの手助けによって伸びるという基本的な考え方のことに対して、固定マインドセットとは、能力や資質は努力したとしても伸びることのないものであるという考え方です。
この成長マインドセットは、スポーツ領域はもちろん、ビジネス領域や人間関係の領域、学校教育や家庭教育、スポーツ教育といった領域で多くの研究もなされています。
競技スポーツで育まれる成長マインドセットの社会的効果
競技スポーツで成長マインドセットが育まれることによる社会的効果として、選手の人生すらも左右されることが考えられます。
なぜならば、物事のとらえ方自体が、マインドセットによって大きく分かれるためです。Brady and Alleyne3)によれば、やる気が下がってしまっている時に、成長マインドセットの人は長期的な視点で自分を見つめプロセスを考え始めます。一方で固定マインドセットの人は、他の人と比べて良い結果が出ない限りモチベーションが上がりにくいです。
その他にも、努力のとらえ方として成長マインドセットの人は「自分の目標達成のためには努力が欠かせないもの」ととらえる傾向にあるのに対して、固定マインドセットの人は、努力を他の人に見せたがらない傾向にあるとしています。
また、成功したときの考え方として、成長マインドセットの人は「ベストを尽くした結果である」と捉えやすく、固定マインドセットの人は、「勝つことは能力が高いから当然のことである」と考えます。
つまり、成長マインドセットの人ほど、結果だけではなくプロセスに意識が向きやすく、固定マインドセットの人は、結果だけに執着しがちです。
成長マインドセットはスポーツ選手に才能をもたらす
スポーツ選手の結果の多くは才能ゆえと思われがちですが、Carol4) によれば、才能が伸びることに対しても2つの捉え方がマインドセットによって異なるとしています。
成長マインドセットの人は、才能や能力は伸びるものであると考え、練習をして努力をします。すべての人は同じ潜在能力をもっていてマイケルフェルプスやマイケルジョーダンといった有名な選手になれる可能性はあると捉えます。
しかし、固定マインドセットの人は、才能や能力は伸びないものであると考えていて、自分には潜在能力がないと考えます。
この考え方の違いは、選手単位だけではなく、チーム単位にすら影響を及ぼします。成長マインドセットを持った選手は、学び・チャレンジを続け・ミスをしたりフィードバックをされたりしても、才能を開花させるためには努力を重要視します。
チーム単位で考えた時には、成長マインドセットを持った選手はコーチの存在はスポーツスキルの上達、情熱をもつこと、努力を続けることや上達したりチームワークを発揮したりするためには欠かせない存在であると認識しやすいです。
また、Tompson5) によれば、才能は努力の賜物であり努力し続けて能力が伸びた結果才能と呼ばれ始めることを述べています。
つまり、自分の能力を高めるうえでは成長マインドセットは非常に大切な考え方であり、成長マインドセットを持った選手は努力することが習慣化するため、結果的にパフォーマンスが高くなり才能が開花する可能性が高いです。
さらに、努力が習慣化することは、学業や仕事といった領域でもとても大切なことはいうまでもありませんが、スポーツには能力を高めるための基本的な考え方を養えるツールの1つなのです。
スポーツ選手への心理的側面に対するアプローチは成長マインドセットを育む
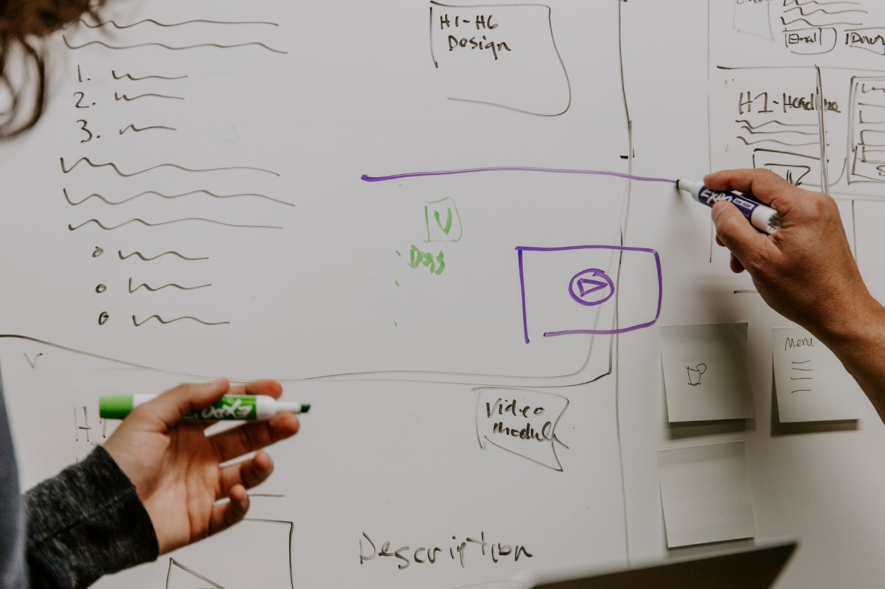
スポーツ選手に成長マインドセットを養ってもらう上では、モチベーションや達成目標が欠かせません。
Carol 6)によれば、マインドセットにおいて重要なことは、能力をどのように考えるかであり、モチベーションや達成目標がとても重要な役割を果たしていることを報告しています。
成長マインドセットを育むうえでは努力はもちろん大切ですが、学び・改善していくことが何より重要であることを述べています。
選手の努力と学びを促し改善するための基本的な心理的スキルトレーニングの1つとしては、目標設定技法があります。
成長マインドセットを育む目標設定
目標設定とは、やる気を高めたりスポーツ選手の練習の質を高めたりするトレーニングとして、メンタルトレーニングなどで行う場合が多いです。また、目標設定を実施する場合は、振り返りも含めたプログラムを提供する場合が多いです。
実際に目標設定と振り返りを50人の女子に介入した研究7) では、目標設定をすることがダーツスキルの向上と高い関係があったことを示しています。
つまり、目標設定はスポーツスキルの向上に役立つ可能性が高く、目標設定や振り返りを含めたメンタルトレーニングプログラムでは、努力をしたことについて振り返りをして学び、次のプレーにつなげるといった一連のプロセスを踏めるように設計してあります。
競技スポーツの選手に役立つ目標設定のやり方
目標設定のやり方として、最も大切なのは結果目標だけではなくそれを達成するために必要なプロセス目標をSMART(スマート)に立てることです。
SMART(スマート)な目標設定とは、下記のような目標であることをいいます。
S: Specific(具体的な目標)
M: Measurable(測定可能な目標)
A: Achievable(達成可能な目標)
R: Related(目標に関連したこと)
T: Time-bound(時間制約がある
このSMART(スマート)な目標設定であることを前提として、競技スポーツ選手にとって効果的な目標設定のやり方は下記の手順です。
1. 自分が最終的にどんな選手になっていたいかを明確に設定する
2. 長期・中期・短期に分けたときの結果目標を逆算して立てる
3. 結果目標を達成するためにどんな練習をしたら達成できるかを設定する
4. 毎日の行動まで具体的に落とし込む
上記のような手順を踏むことによって、やるべきことが明確になるためやる気や練習の質が高まり、スポーツも上達していきます。
このような一連のプロセスを繰り返し踏むことによって、スポーツ選手の成長マインドセットを育むことにもつながりやすく、競技スポーツに取り組む社会的な意義が生まれるのです。
まとめ
今後の競技スポーツは、日本社会において価値のあるものになっていくと、スポーツで社会的人材が育つ日本社会になるでしょう。
特に成長マインドセットは、近年スポーツ教育領域で注目されている概念であり、スポーツで培った成長マインドセットは、勉学や仕事にも活かされる可能性が高いです
成長マインドセットを育むために心理的側面に対するアプローチはとても効果的で、その1つの方法として目標設定があります。
練習と目標設定と振り返りをする一連のプロセスを踏むことによって、成長マインドセットを育む1つの助けになるでしょう。
本記事で、競技スポーツの社会的意義について参考にしていただければ幸いです。
引用参考文献
1) 浜口義信(1983).スポーツ概念の意味論的研究―特に言語的意味論を手がかりとして― スポーツ教育学研究,2:73-80.
2) Carol S. Dweck (2006). Mindset: the new psychology of success Ballantine Books.
3) Abbe Brandy and Rudy Alleyne (2018). Positive psychology in sport and physical activity, Ed. Abbe Brandy and Bridget Grenville-Cleave, Routledge.
4) Carol S. Dweck (2009). Mindsets: Developing talent through a growth mindset Olympic Coach21 (1): 4-7.
5) Jim Thompson (2018). Elevating your game Balance Sports Publishing.
6) Carol S. Dweck (2015). Carol Dweck Revisits the ‘Growth Mindset’ Education Week. (最終閲覧日2020年5月9日)
7) Barry J. Zimmerman and Anastasia Kitsantas (1996). Self-regulated learning of a motoric skill: the role of goal setting and self-monitoring journal of applied sport psychology, 8: 60-75.
基本情報
| 名前 | 後藤晃一 |
|---|---|
| ご所属 | CoGno代表 メンタルトレーニングアドバイザー NPO法人スポーツコーチング・イニシアチブ 事務局 NPO法人Compassion メンタルトレーニングコーチ |
| メールアドレス | koichi-consultant@applie-psychology.email |
| プロフィール | 競争を競創へをコンセプトにした人財育成を軸に活動をしています。世の中には多くの競争がありますが、競争は本来優劣をつけるだけに留まりません。切磋琢磨し、共に努力することが競争の本質的な意味です。切磋琢磨するための心理的スキルを育むメンタルトレーニングプログラムの提供や環境づくりを通した社会的仕組みづくりといった活動を通して、スポーツの社会的な価値を高めたいという想いのもと日々活動しています。 |